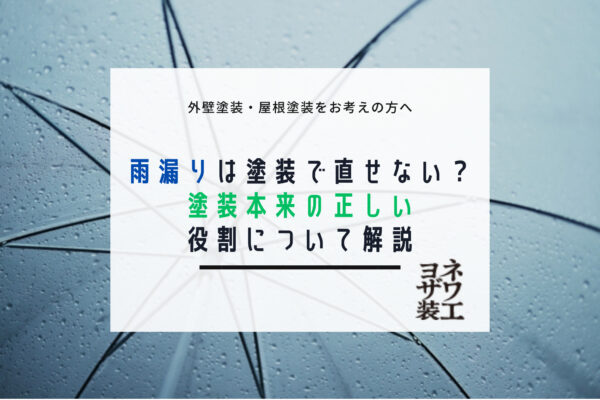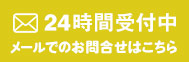屋根塗装に必要な「タスペーサー」とは?役割と重要性について解説
2024/06/20
タスペーサーは、平板スレート屋根の重なり部分の隙間に押し込んで、適切な隙間を確保できるようにするための部品です。
平板スレート屋根の塗装工事を行う前にタスペーサーを押し込む工程が加わることがあります。
では、屋根塗装において、タスペーサーはどのような効果があるのか解説します。
屋根塗装でタスペーサーが必要な屋根とは

屋根塗装でタスペーサーの利用が検討されるのは、平板スレート屋根の場合です。
平板スレート屋根は、スレートという厚さ5ミリ程度のセメント板を重ね合わせる工法で、瓦屋根に比べると軽いため、地震に強い住宅を建てることができるのが特徴です。
平板スレート屋根の塗装によるメンテナンスが必要なタイミング

平板スレート屋根は厚さ5ミリ程度と薄いだけにメンテナンスを怠ると雨漏りや屋根の野地板の腐食につながってしまいます。
特に、スレート自体はセメントを固めた板なので防水性能がなく、塗装によって防水性能を維持している点に注意が必要です。
平板スレート屋根に次のような劣化症状が現れたら補修や塗装が必要になります。
色褪せ
地上から見て、平板スレート屋根が色褪せているのが分かる状態だと、長年紫外線や雨水に晒されたことにより、塗膜の表面の劣化が進んだものと判断すべきです。
塗膜が劣化すると雨水を弾かなくなり、スレート自体も痛みやすくなるため、早めに塗装を検討すべきです。
コケやカビの発生
地上から見て、平板スレート屋根が色褪せているだけでなく、コケやカビが発生しているのがわかる状況だと、スレートの塗膜が劣化し防水性能が失われていることになるため、早期の塗装が必要です。
塗膜の剥離
地上から見て、平板スレート屋根の塗膜が剥離しているのがわかる状態だと、すでにスレートが雨水を吸水している可能性が高いです。このまま放置すると、スレートがさらに劣化し、割れや欠け、脱落につながってしまい、屋根材自体の交換が必要になります。
反り、浮き
地上から見て、平板スレート屋根の反り、浮きを確認できる状態だと、スレートの防水性が失われて、雨天時の吸水と晴天時の乾燥を繰り返している可能性があります。反り、浮きが大きくなるとその隙間から雨水が侵入しやすくなりますし、台風などの暴風時は、スレートが剥がれやすくなります。
平板スレート屋根の塗装工事の流れ

塗装工事は次の流れで行われます。
✅下地処理、高圧洗浄、欠け・割れの補修等
✅下塗り
✅中塗り
✅上塗り
✅点検、仕上がり修正
平板スレート屋根を塗装する際は、上塗りの後で「縁切り」と呼ばれる工程が必要になります。
平板スレート屋根の塗装を行うと、スレートの重なり部分が塗膜によって塞がれてしまうことがあります。重なり部分も塗膜で塞げば、雨水が浸透しないので、防水性が高まるのではないかと思われるかもしれませんが、実は逆で、却って雨漏りの原因になってしまうこともあります。
スレートの重なり部分には4ミリほどの隙間がありますが、この隙間は屋根の内部に染み込んでしまった雨水や屋根材裏面の湿気を排出する役割を担っています。
そのため、この隙間を塞いでしまうと、雨水や湿気が屋根の内部に溜まってしまい、野地板を腐らせたり、雨漏りを発生させる原因になってしまうのです。
そこで、上塗り工程の後で、重なり部分の塗膜をカッターなどで切る「縁切り」作業を行う必要があります。
縁切りは面倒な作業の上、様々な欠点もあることから、縁切りを省略できるタスペーサーが広く使われるようになりました。
縁切り工程の欠点
縁切りは、塗膜によって塞がれたスレートの重なり部分にカッターや皮スキなどで切り込みを入れて、水の通り道を確保する作業です。
ただ、カッターでは塗膜に刃が入りにくく作業効率が悪いため、皮スキで塗膜を剥がすのが一般的です。
皮スキを使った縁切り作業では、スレートの重なりの隙間に皮スキを押し込んでスレートを持ち上げるようにして塗膜を剥がします。
そのため、力の入れ加減を間違えると、スレートを破損してしまうリスクがあります。
さらに、塗膜が完全に乾いてから作業を行うわけではないため、後日塗膜が密着してしまう可能性もあります。
そして、何より残念なのがせっかく塗装した屋根に上がるため、足跡が残ってしまったり、屋根の端の小口部分が破損してしまう可能性もあることです。
タスペーサーを使った屋根塗装

タスペーサーを使った屋根塗装では、縁切り工程が不要になります。
具体的には、下地処理の段階で、スレートの重なり部分の隙間にタスペーサーを押し込み、適切な隙間と通気性を確保するため、上塗り後の縁切りが不要になるわけです。
タスペーサー工法の特徴を見ていきましょう。
あらかじめ十分な隙間を確保できる
下地処理の段階でタスペーサーをスレートの重なり部分の隙間に挿入しておくことにより、重なり部分の十分な隙間を確保することができます。
具体的には500円硬貨を差し込めるほどの隙間を維持することができます。
そのため、下塗り、中塗り、上塗りの3度の塗装を行った後でも、隙間が塗膜により塞がれることはないため、縁切りが不要になるわけです。
タスペーサー挿入作業は短時間で終わる
縁切り作業を行う場合、職人2名で行っても丸1日かかってしまいます。
下地処理の段階でタスペーサーを挿入する作業は、一般的な広さの屋根ならば、約2〜3時間で終えることができます。
上塗り後のスレート破損のリスクが少ない
縁切り作業は上塗り後の屋根に上がっての作業になるため、せっかくきれいにした塗装面を汚してしまったり、縁切りによってスレート自体を破損させてしまうリスクがありました。
タスペーサーを挿入しておけば、上塗り後の縁切りが不要になるため、こうしたリスクがなくなります。
タスペーサーは抜く必要がない
上塗り後、タスペーサーは挿入したままで、撤去する必要がありません。また、タスペーサーの素材は、塗装がなじむため目立たなくなります。
ただ、よく見れば、タスペーサーが挿入されているかどうかは一目瞭然なので、すべての工程を完了した後で、職人さんに屋根の写真を撮ってもらうことで、タスペーサーが適切に挿入されているかどうかを施主様も確認する事ができます。
タスペーサー工法の単価と価格
タスペーサー工法の単価は1平方メートルあたり、300円〜500円程度が相場とされています。
また、一般的な住宅で使うタスペーサーの個数は1000個前後です。
タスペーサーは、ホームセンターやネット通販でも販売されていますから、おおよその単価がわかると思います。
一方、従来の縁切り工法を行った場合は、職人2名で丸一日かけての作業になるため、1平方メートルあたり、500円〜800円程度のコストがかかります。
つまり、タスペーサー工法を採用した方が塗装費用を押さえられるということです。
タスペーサー工法も縁切りも行わない場合

屋根塗装でも、タスペーサー工法と縁切りのどちらも行わない場合があります。
平板スレート屋根以外の屋根の場合
タスペーサー工法や縁切りが必要になるのは、基本的に平板スレート屋根だけです。
セメント瓦、モニエル瓦等の場合は、十分な隙間があるため、基本的に縁切りの必要はありません。
ただ、最近主流となっているガルバリウム鋼鈑の屋根材を塗装する際は、屋根の形状によっては、縁切りが必要なので注意が必要です。
具体的には、縦葺きの場合はそもそも継ぎ目がないため、縁切りが必要ありません。一方、横葺きの場合は、スレート屋根と同様の葺き方をしており、継ぎ目が設けられているので、縁切りが必要になります。
塗装工事を初めて行う場合
平板スレート屋根は塗装を行っていない段階であれば、スレートの重なり部分に十分な隙間が確保されているため、一回塗装を行った程度では、よほどてんこ盛りに塗らない限り、その隙間が塗膜で塞がれることはありません。
また、スレートは直射日光が当たることにより自然に外側に反るようになっているため、隙間が塞がれてしまうことを心配する必要はありません。
2回目、3回目と塗装工事の回数を重ねている場合は、塗膜が盛り上がって厚くなるため、スレートの重なり部分の隙間がふさがりやすくなるので、タスペーサーの挿入や縁切り作業が必要になります。
経年劣化によりスレートが反っている場合
経年劣化によりスレートが反っていて、タスペーサーを挿入しても抜けてしまうほどの隙間がある場合です。
このような場合は、タスペーサーの挿入も縁切り作業も不要となることがあります。
もちろん、スレートの劣化の程度によっては、塗装よりも屋根材の交換が必要な場合もあります。
急傾斜の屋根、勾配の大きい屋根の場合
急傾斜の屋根、勾配の大きい屋根ならば、塗装時の塗料が自然に下に流れるのでスレートの重なり部分が塗膜で塞がれにくく、タスペーサーの挿入も縁切り作業も必要ないこともあります。
屋根塗装を吹付け工法により行う場合
スレートの重なり部分が塗膜で塞がれやすいのは、ローラーによる塗装を行う場合です。
ローラーによる塗装では、スレートの重なり部分にローラーを押し当てるように塗装することになるため、重なり部分に塗料が大量に吐出されやすくなります。そのために隙間が塗料によって塞がれやすくなるわけです。
吹付け工法の場合は、屋根の全体に均一に塗料を吹き付けることができるため、スレートの重なり部分に塗膜が集中することはありません。
そのため、スレートの重なり部分が塗膜によって塞がれにくいので、タスペーサーの挿入も縁切り作業も必要ないこともあります。
平板スレート屋根塗装の見積もりで注意したいこと

平板スレート屋根の塗装工事を依頼する際は、
✅下地処理、高圧洗浄、欠け・割れの補修等
✅下塗り
✅中塗り
✅上塗り
✅点検、仕上がり修正
という、塗装工事の基本的な工程を行うかどうか確認することはもちろんですが、「縁切り」はいつ行うのかを必ず確認するようにしましょう。
上塗り塗装の後で、縁切りを行いますと言っている場合は、タスペーサーを使わず、従来通りの縁切り作業を行うことを意味している可能性が高いです。
縁切り作業は、スレートを破損させるリスクもあるため、できれば、タスペーサーを挿入することで省略できないのか相談してみるべきでしょう。
下塗り段階でタスペーサーを挿入するという説明ならば、上塗り後のスレートの破損のリスクが少なくなるため、安心と言えます。
また、見積書では、縁切り工程の材料としてタスペーサーを使うのかどうかをチェックしましょう。タスペーサーの記載がない場合は、縁切りをどのようにやるのか確認すべきです。
もちろん、平板スレート屋根塗装でも、タスペーサー工法も縁切りも必要ない場合もあります。
縁切りは必要ないと言われた場合は、その理由を問いただし、納得できる説明を受けてから塗装工事を依頼することが大切です。
千葉県市原市での屋根塗装の悩みはヨネザワ装工へご相談ください
ヨネザワ装工は千葉県市原市を中心に地域密着で屋根や外壁の塗装工事などを行っている職人直営店です。
実際に塗装工事を行う職人へご依頼になるため、中間マージンがかからず、本当に塗装工事に必要な費用のみでご依頼いただけます。
平板スレート屋根の塗装工事も数多く行っており、仕上がり後の縁切り作業も丁寧に行わせていただいております。また、お客様のご要望やお家の状況に合わせて、タスペーサー工法も採用しております。
また、屋根塗装をご依頼いただく際は同時に外壁塗装もご依頼いただくことも多いです。どちらも丁寧に厚く塗って、長期間にわたり、お客様のお家を保護できるようにいたします。
千葉県市原市で屋根塗装に関するお悩みがある方や工事をご検討されている方は、ヨネザワ装工へご相談ください。